こんにちは、かしわぎです。
今年2025年の11月に日本のバイク業界に大きな変化が訪れます。新車の製造が終了する50cc原動機付自転車(以下、原付)に代わって原付免許・普通自動車免許で運転できる125ccクラスのバイク、新基準原付の登場です。
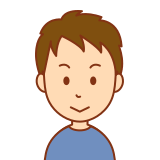
え!自動二輪免許持ってなくてもホンダ・GROMとか乗れるってこと?ラッキー!なに買おうかなあ!

ちょっと待って!この新基準原付っていうのは今までの125ccバイクとは違うんだ。わかりやすく簡潔にまとめてみるよ!
- 新基準原付とは50ccバイクの性能・仕様に合わせた125ccクラスのバイク
- 新基準原付は従来の50ccバイクと同様のルールで運転する
- 従来の125ccクラスのバイクは普通自動二輪車免許が必要
つまり新基準原付の規格に対応したバイクは、今までの50ccバイクと同じルールで運転する必要があるということです。
今回は、これから発売される新基準原付とはなんなのか、通常の125ccバイクとの違いはなにかといった解説をしていきます。
「原付免許で運転できる125ccバイク」は半分正解半分間違い
新基準原付とは、既存の50cc以上~125cc未満のバイク(以下、原付二種)の車両を現在の50cc以下のバイク(以下、原付一種)の規制や規格・仕様に適合させた車両のことです。この新基準原付は普通自動車免許や原付免許を持っていれば運転できます。
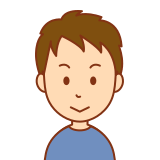
がんばって普通二輪免許取ったのに、自動車乗りがいきなり125ccのバイクに乗れるようになったら納得いかないなあ!!!

落ち着いて……。実はこれ、125ccであって原付二種ではないんだよ。
混乱するのも無理はないでしょう。実際にこのニュースを聞いて「原付免許で二人乗り出来るバイクに乗れる」とか「これからの原付は30km/hの速度制限から開放される」と勘違いしてしまっている人もいるのではないかと思います。「原付免許で現行の原付二種と同じ車種に乗れる」と点に限って言えば、半分正解で半分間違いですからね。その先行した認識から上記のような勘違いをしてしまった……というのも分からなくはありません。
ルールが少々ややこしいので、次項から新基準原付とは何かをわかりやすく整理しながら解説していきます。
生産終了する50ccの代役として登場するのが新基準原付
そもそも新基準原付とはなんでしょうか。登場のきっかけは、2025年11月1日より施行される新たな環境規制である国内第4次排ガス規制でした。
これは2022年10月に施行されたユーロ5という欧州排ガス規制の日本国内版である平成32年度(令和2年度)排ガス規制を原付一種に適用したものです。
一般的に排気ガスは触媒という浄化装置でクリーンにして排出しており、この触媒はエンジンの排熱で温めることで性能を発揮します。第4次排ガス規制では触媒が温まる前に計測する必要があるため、原付一種の排熱量では触媒が十分に温められずに排気ガスを浄化できない=厳しい排ガス規制を通せない=適合できない原付一種のバイクたちは軒並み生産終了、というわけです。
しかし、年々減少傾向ではありますが、未だ日本全国の保有台数が約433万台、年間10万台前後の販売台数と二輪車全体のうち23%の構成比をもつ原付一種は、手軽な交通手段として重要であることに違いはありません。
参考: 一般社団法人 日本自動車工業会 二輪車生産・販売台数統計

日々の買い物や通勤に原付一種はまだまだ必要な存在。
なにか代わりになる乗り物が必要だよね……。
日本をはじめ海外の大手バイクメーカーの技術力をもってすれば50ccのエンジンでも規制をクリアできるものが作れるでしょうが、その莫大な開発費と高価になった装備分のコストが車両代に反映されます。しかも50ccのバイクというジャンルと免許制度自体が日本とヨーロッパの一部にしか無く、グローバルモデルのように大量生産による売上が期待できないので、必然的に一台あたりの価格も高くなります。もし6~70万円もする50ccバイクが発売されても高すぎてちょっと……と、ほとんどのユーザーは躊躇しますよね。かかるコストの割に売上が見込めないので開発・生産が困難なのです。ついでにいえば、規制を通せる程度の出力に留めた場合は登坂能力が著しく低下し、坂道の多い地域で十分な走行性能を発揮できなくなるという難点もあるようです。
そこで規制を通せる現行原付二種をベースに、より安価な代用原付一種を用意するというのがこの新基準原付導入の目的なんですね。
その規制に先駆け、2025年4月1日の原付区分の改正によって登場するのが新基準原付です。
しかし今のところ新基準原付は1台も販売されていません。現行の原付一種が2025年11月から新車販売ができなくなるので、そのタイミングで入れ替わるように新基準原付が登場するのではと予想しています。
ちなみに50ccのガソリンエンジン車は販売終了しますが、原付一種の区分自体は消滅せず、電動バイクや電動モペットといった車両が引き続き区分されます。
新基準原付と原付一種・二種の違いは排気量だけじゃない

ここで新基準原付の交通ルールや区分についての違いを表にまとめました。運転する上でのルールなどを整理しておきましょう。
| 原付一種 | 新基準原付 | 原付二種 | |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 50cc以下※1 | 50cc以上125cc以下※2 | 50cc以上125cc以下 |
| 最高出力 | 4.0kW以下※1 | 4kw(5.4PS)以下※2 | – |
| 免許 | 原付免許以上 | 原付免許以上 | 小型限定普通二輪免許(AT限定含む)以上 |
| 最高速度 | 30km/h(一般道) | 30km/h(一般道) | 60km/h(一般道) |
| ナンバープレート | 白 | 白 | 黄色orピンク |
| 二段階右折 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 最大積載量 | 30kg | 30kg | 60kg |
| 二人乗り | ✕ | ✕ | ○ |
| 高速道路走行 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 軽自動車税 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円※3 2,400円※4 |
※2…どちらの条件も満たす必要がある
※3…原付二種乙種 (50~90cc・黄色ナンバー)
※4…原付二種甲種 (90~125cc・ピンクナンバー)
表を見比べると、新基準原付は排気量と最高出力の制限以外は原付一種と全く同じ交通ルールで運用されることが分かると思います。
次は新基準原付を運転する上で重要なポイントをピックアップしてみます。
原付免許で運転できるバイクは従来の原付一種と新基準原付だけ
新基準原付の登場により、運転免許の内容に変化があるのでしょうか。
端的に言うと免許毎に運転できる車両の種類は変わりません。原付免許で運転できる車両に新基準原付が加わるだけです。2025年11月になっても原付免許や自動車免許で原付二種が運転できるわけではありません。
新基準原付は「パワーを落とした代わりに原付免許で乗れるようになった原付二種」ではなく「原付免許で乗れるように仕様変更した原付一種のルール内で走れる125ccクラスバイク」ということです。
前者の認識でいる方は、
125cc=原付一種のような規制がないバイク=原付二種という図式
が頭の中にできているため、「原付免許で二人乗り出来るバイクに乗れる!」とか「新基準原付に乗れば30km/h制限から開放される!」といった勘違いが起きてしまうのではと思います。

変わるのは免許じゃなくて車両区分の方という点に注意しよう!
ナンバーは白!二人乗り禁止や30km/h制限のルールは全部原付一種と同じ

上記の表にも書きましたが、新基準原付のルールは原付一種と基本的に同じです。ナンバープレートは白、年に一回支払う軽自動車税も同様に2,000円です。
当然二人乗りは禁止ですし、制限速度は30km/hで二段階右折もしなくてはなりません。第1通行帯通行義務(いわゆるキープレフト)も同様です。排気量だけで道路交通法の認識を区別していると、新基準原付で二人乗りをしたり二段階右折を無視してしまったりといったトラブル発生のおそれがあります。
新基準原付は原付一種と同じ、と意識することが重要です。
従来の原付一種はそのまま乗ってOK!規制以前のバイクの売買もOK
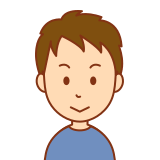
11月の規制で50ccバイクがもう売れなくなるんだよね?
新基準原付は高いから中古の50ccスクーターを買いたかったんだけど、11月以降に道路を走ったら違反になるの?

それは大丈夫、新規制が適用されるのは11月以降に発売される車両だけだよ!
2025年11月以降に施行される国内第4次排ガス規制が適用されるのは、同月以降に新車販売される車両のみなので、2025年10月31日までに製造された車両なら公道走行が可能です。バイク屋に生産終了した50ccスクーターの新車店頭在庫があれば、11月以降の新排ガス規制が適用された後に購入して運転しても問題ありませんし、それが10年前の中古50ccバイクだったとしても同様です。
排ガス規制前後で採れる選択肢を再確認してバイク購入を検討しましょう。
コンセプト車のスーパーカブライトを見て空想する
2025年3月に東京ビッグサイトにて開催された東京モーターサイクルショーに参加した際、ホンダブース内に新基準原付のコンセプトモデルであるスーパーカブライトが展示されていました。試作車とはいえ、新基準原付はどういうものかというユーザーの疑問に、初めてメーカーからの具体的な回答が出たのは大きいです。
いい機会なのでジロジロ観察してきました(そのわりに写真は少ない上にいい加減)ので、新基準原付と原付二種の外見・構造的違いや気付いた点について説明していきます。
東京モーターサイクルショー2025に参加したレポ記事はこちら。よろしければこちらもどうぞ。

スーパーカブ50の段階でかなりの部分が共通だったので当然ですが、外観はスーパーカブ110からほとんど変わりません。

外観はカブ110ほぼそのまま。フロントパネルにSuper Cub Liteのステッカーが付く程度でしょうか。

原付一種の規格に合わせてメーターの60km/hスケール化&速度警告灯が追加されています。速度表示の下にギア毎のカバー範囲が記載されているのですが、カブライトでは3速までの表示となっています。カブライトはギアを4速から3速に変更してリリースされる可能性が出てきました。これは多少のコストダウン効果以上に機械的な速度リミッターとしての役割を持たせる変更ではと思っています。
ただ、たとえ最高60km/hでリミッターがかかるとしても、ギア数が多ければ回転数と振動を抑えることが出来ます。4速ギアの快適さを知ってしまうと3速がかったるくて仕方ありません。好みの問題もあるでしょうが、僕個人としてはカブライトも4速ギアのままリリースしてほしいです。果たしてどうなるでしょうか。

当然二人乗りができないので、スイングアームからはタンデムステップとマウント部がオミットされています。サスペンションのセッティングも多少変更があるかもしれません。

一方で規制と無縁の足回りなどは基本そのままのようです。アルミキャストホイールやフロントディスクブレーキはカブ110のまま、ABS装備も同様でした。原付一種と新基準原付はABS・前後連動ブレーキの装備義務がないため、カブ50と同様のスポークホイール+ドラムブレーキを流用してコストダウンを図ることも出来ます。僕はこのカブ110のままの構成のほうが走行性能が高くて良いと思います。あくまで現状はコンセプトモデルなので注目していきたいところですね。
新基準原付への期待と懸念
上記のスーパーカブライトを観察してみると、新基準原付としての変更は最小限に留めているように感じました。
原付一種と同程度の仕様に変更された新基準原付のスーパーカブ110と従来通りの原付二種のスーパーカブ110が同時に販売され店頭に並ぶようになるというわけです。
車体自体はほとんど同じように見えるので、新基準原付について知らない方は混乱することもあるのではないでしょうか。当然区分は原付一種と二種で異なるため、混同しないように注意しましょう。
リミッター解除は複雑?不正改造は大幅に対策されそう。
60km/h以上の速度が出せるようにするリミッター解除という原付一種には定番の改造が存在します。一部カスタム好きな方の中にはリミッターカットしたいと思っている人もいるのではないでしょうか(改造自体は違反の対象では有りませんが当然スピードの出し過ぎによる安全性や速度違反の対象となるリスクはあります)。
ここでは速度・出力制限(リミッター)について解説していきます。
警察庁主催の有識者検討会報告書によると以下のようなリミッター構造を検討中と記載があります。構造としては以下の通り。
- スロットル開度の規制等、物理的な制御 (今回の試作車に採用)
- 燃料噴射コントロール等、コンピューター(ECU Engine Control Unit)による制御
- 1と2の組み合わせ
どのパターンでも次のA、Bどちらかの制御とされており一般人による改造が困難になるような構造にされるとのことでした。
【A】物理的制御:工場等で使用されているもの以外の工具では、出力制御のために変更した部位にコンタクト出来ない特殊な構造
【B】 ECUによる制御:カードの差し替えや、断線や短絡等による出力制限の解除は不可とする設計
現状では、テスト用車両に採用された上記1のようなスロットル開度制限などの物理的制御が有力なように感じます。もしかすると3番のように複合的なリミッターとなることもあるかもしれません。
さて、ここで東京モーターサイクルショーでカブライトを見学した時に、ホンダブースの方にちらりとお話をお聞きした内容を書いておきます。うろ覚えなのでだいたいこんな感じ、という程度の認識でお願いします。

カブライトはこのまま発売されるんですか?
速度リミッターはどうなるんでしょうか?
あと他の新基準原付の車種について教えて下さい!
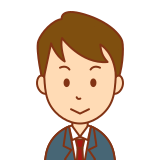
これはコンセプトモデルなので変更があるかもしれません。
リミッターはECUなどの電子的なものと機械的なリミッターを併用すると思います。
他の車種は現状未確定なのでお伝えできません。発表までお待ち下さい。
新基準原付の車種についてはわかりませんでしたが、速度リミッターの件がお聞きできました。ECUでの制御は当然ながら、機械的なリミッターも併用するようなので、カムシャフトやスロットルボディ、ミッションやスプロケット(スクーターならギアボックスのファイナルギアなど)といった箇所の変更で速度を抑制するということです。
この場合、原付二種版のECU以外にも新基準原付規制版部品も交換しないとリミッター解除は出来ないはずです。
新基準原付を安く購入した後に普通二輪免許を取得した場合、もしリミッター解除ができれば安価に原付二種に乗ることができます。車両を丸々乗り換える必要もありません。しかし交換部品代と工賃などを考慮すると、素直に原付二種版を購入した方が費用面でも安全面でも賢い選択ではないでしょうか。メーカー純正のままなら当然保証も有効です。というかその予算で素直に普通二輪小型限定免許を取得したほうがいいですね。
普通二輪免許を不所持のユーザーが不正改造を施し原付二種化して無免許運転を行うといった懸念がありましたが、この複雑なリミッター構造によりその心配も減るのではと思います。安心安心。
原付用駐輪場の利用は問題なさそう?よく使う場所は事前確認を
もうひとつ懸念がありました。駐輪場問題です。
僕の生活圏内にある駐輪場の多くが125cc以下のバイクを駐輪可能です。
しかし、自転車駐輪用途がメインでスペースに余裕がない一部の駐輪場には、50cc以下のバイクのみ駐輪可能という場所も存在しています。
この50cc以下のバイクのみという制限が問題で、新基準原付は白ナンバーながら車体と排気量は125ccのまま。駐輪場オーナーの判断によりますが、もしかすると新基準原付が停められないという場所も出てくるのではないでしょうか。自転車利用者のための駐輪場が主目的であれば尚更、デカくなったバイクのためにスペースを割り当てることも難しいでしょう。
通勤や買い物で頻繁に利用する駐輪場がある方は、予め駐輪場の管理会社へ確認するのが安心かもしれません。
従来の原付一種と比較した新基準原付のメリット・デメリット
原付一種から新基準原付に乗り換える時に問題はないのでしょうか。現行の原付一種と新基準原付を比較したメリットとデメリットを挙げてみます。ちなみに新基準原付の車両はまだ発表されていないため、暫定でスーパーカブ110とディオ110といった車両を新基準原付化したものと想定しています。
- 装備が豪華
- パワフル
- 燃費が良い(予想)
- 高価
- 大きい
- 重い
最大のメリットは装備が豪華になることです。上位クラスの原付二種の車体を基本そのまま使用するので、安定した制動力のディスクブレーキや明るく省電力のLEDライト、多機能デジタルメーターなどの便利装備の恩恵に預かれます。
新基準原付は最高出力を5.4PSに規制されても、多くの原付一種よりだいたい1馬力以上パワーが上です(全車が上限の5.4PSに調整されるとは限りませんが)。排気量はそのままなので出力に余裕があり、原付一種と同速度で走行した際にエンジン回転数が抑えられる=エンジンの負荷が少ない低燃費走行を実現しやすいというメリットもあるでしょう。
一方でデメリットも、原付二種の車体を使用することに起因します。例えばホンダの現行原付一種のスタンダードモデルであるタクト・ベーシックと原付二種のディオ110ベーシックを比較してみましょう(ディオ110は新基準原付として発売するかはわかりません。あくまで例として挙げておきます)。
| タクト・ ベーシック | ディオ110・ ベーシック | タクトを基準とした ディオ110 | |
|---|---|---|---|
| 車重 | 79kg | 96kg【95kg】 | +16kg |
| シート高 | 705mm | 760mm | +55mm |
| 全長 | 1,675mm | 1,870mm | +195mm |
| 全幅 | 670mm | 685mm | +15mm |
| 全高 | 1,035mm | 1,100mm | +65mm |
| 価格(税込) | 179,300円 | 250,800円 【227,800円】 | +71,500円 【+48,500円】 |
まず第一に高価になります。メーカーも原付一種から乗り換えるユーザーのために多少価格を下げてくれるかもしれませんが、それでもベースは原付二種そのままなので、20万円程度で購入できる安価な車両は期待できないかもしれません。
同様に原付二種をベースにすることで車重・車格の大幅なアップが予想されます。数ある原付二種の中でも軽量スリムなディオ110を例に挙げましたが、それでもタクト比で+16kgの車重、+55mmのシート高です。小柄な方はこのあたりのサイズアップは普段の使用感に影響が出るかもしれません。
軽量コンパクトな車種なら慣れでカバーできるレベルだと思いますが、車種選定は慎重に行う必要があるでしょう。
新基準原付として登場する車種を勝手に予想する
ここまでの解説で新基準原付について理解できたと思いますが、実際どんな車種が販売されるのでしょうか。現状で正式に発売が告知された車両は皆無で、唯一公式の場に現れたスーパーカブ110ライトもコンセプトモデルのため、あの姿のまま発売されるかは定かではありません。
そこで僕が新基準原付のラインナップがどうなるのかを予想してみます。
当然ですがこのラインナップ予想はメーカーの方から聞いたりといった根拠はありません。すべて僕の空想・妄想であり脳内にのみ存在するカタログです。ご注意ください。
出力規制などのルールは規定のものがあるのでその部分は準拠するとします。その他に僕が新基準原付に求める基準は以下の3点です。
- 車重は120kg以下
- 価格は高くても30万円前半
- あくまでも移動の手段としてのラインナップ
1.は僕の体感から勝手に決めました。NMAXやPCXといった車重が120kgを超える大きめの原付二種を押し引きすると明らかな重さを感じます。狭い駐輪場内や路地での取り回しが大変だと、原付一種からの乗り換えを躊躇してしまうのでは、と思います。
できれば100kg+5kg上限くらいが理想で、このくらいであれば「慣れれば何とかなりそう」と思えるのではないでしょうか。
もちろん体格などによってはこの限りではないので、一度バイク屋に置いてあるバイクに跨がらせてもらうなどして感覚を掴んでおくのをオススメします。
2.の価格面も原付一種からの移行のハードルを下げることが目的です。各メーカーには魅力的な原付二種が数多くラインナップされていますが、新基準原付化するにあたっての問題はその価格です。30万円後半~という価格設定の上級モデルも多く、その中の趣味性の高い車両には50万円を超える価格設定も。
魅力あるモデルも多いですが、新基準原付の目的は原付一種からの乗り換え需要に応えるためというのが大前提。残念ですが高価なモデルの登場は見送りになるでしょう。
ちなみに次項の登場車種予想の希望価格は、ベースとなる現行原付二種モデルから2,3万円~安価に設定しています。元の車体から削減できる部分がほとんどないので普通に考えれば同価格でもおかしくありませんが、「下位モデルは安くなって当然」と思う方も少なくないと思います。ということでこの価格設定は心情的な面での値引きが入っています。1円でも利益を上げたいメーカーが涙をのんで安くしてくれるのはありがたいですね(現状は僕の脳内での話ですが)。
3.の条件はここに当てはまります。新基準原付はあくまで日々の移動手段というポジションで販売されるのが現状の最適解ではないでしょうか。
原付免許で乗れるMT車が久しぶりに登場すればバイク好きとして嬉しいことですし、これをきっかけにバイクユーザーが増えてくれれば良いと思いますが、趣味性の高さやかなりの高価格という点が新基準原付の目的にそぐわないですし、現在の市場規模的に現実的ではなさそうに感じます。
もちろんカブのような、ある程度趣味性が高い車種が登場するのは期待できそうです。キャンプやツーリングなどの遊びに使いたいという方はこのあたりを購入候補にするのもいいかもしれません。
次項からは僕の独断と偏見で新基準原付のラインナップを予想していきます。
名称については、現状唯一の新基準原付コンセプト車両であるスーパーカブにライトの名称が付いていたため、ここでは便宜上〇〇(車種名)ライトという記載とします。
※警察庁の新基準原付走行評価も参考に。PCXやCB125Rは個人的には無し
参考に、令和5年に警察庁主導で実施された新基準原動機付自転車に係る走行評価というものがあります。
新基準原動機付自転車に係る走行評価結果について
新基準原動機付自転車に係る走行評価
新基準原付は低速トルクがあり発進しやすく安定感があるといったコメントが多く、思いの外好感触のようでした。意外にもPCXの評価が高いようでしたが、僕個人の意見としては価格面がネックになると思い候補から外しています。また、新基準原付の重量や大きさが初心者が乗る際のハードルになるという指摘もあったため、自身の経験と照らし合わせて他の重量のあるバイクも候補から外しました。
僕としても好きなバイクのCB125Rも試験車両に含まれていましたが、上記理由によりハードルが高いように思うため候補からは除外しています。

繰り返すけど全て妄想だよ。僕の予想通りのラインナップでリリースされる保証は全くないから、あくまで話半分に!
【空想】ホンダはカブライトを筆頭に多彩なラインナップが武器
- スーパーカブ110ライト
- スーパーカブ110プロライト
- Dio110ライト
- LEAD125ライト
まずは大本命のホンダです。コンセプトモデルとはいえ、3メーカーの中で唯一新基準原付のスーパーカブライトを提案してきており本気度の高さが伺えます。
原付二種ラインナップの豊富さを活かして、ビジネスユース、街乗り、買い物などユーザーのニーズに沿った最適な車種を見つけられます。ディオ110とリード125はアイドリングストップ機能付で燃費性能も優秀です。
ホンダの原付二種は他にもダックス125やGROMなど魅力的な車種が多数ラインナップされています。しかしどれも高価なため今回はラインナップから外しました。
スーパーカブ110ライト 希望価格 税込259,500円

当然コンセプトモデルが存在するスーパーカブ110ライトは、ABSや前後連動ブレーキの装備義務の無い新基準原付として登場するのがポイント。コンセプトモデルの3速ギア化と、カブ50のスポークホイール+ドラムブレーキを流用すれば更なるコストダウンが図れるのでは、という期待を込めてこの価格です。スポークホイール&ドラムブレーキにすればベースのカブ110よりクラシカルなスタイルになり、カジュアルに乗りたい層からの人気も期待できます。旧型カブ110プロの14インチスポークホイールを流用したリトルカブライトのようなバリエーションモデルがあっても良いかもしれませんね。
カブシリーズ伝統の優秀な燃費性能はそのまま受け継いでいるでしょうし、維持費を抑えて長く付き合える一台になるでしょう。
ただ僕個人としては、ディスクブレーキの安心感とチューブレスタイヤの利便性を重視して、多少高価になっても走行性能のアップを図る方がいいのではと思います。部品の共通化と量産効果で多少のコストダウンにはなるでしょう、多分……。
スーパーカブ110プロライト 希望価格 税込326,500円

スーパーカブ110プロライトは新聞配達などのビジネス用途で一定の需要があると見込んで採用。ビジネススクーターより登坂にも強いですしね。
カブ110と同様の理由で、カブ110プロと同じキャストホイール+前輪ディスクブレーキのまま登場が望ましいです。特に、天候や路面状況に関係なく毎日稼働しなければならないビジネスユースでABS付きブレーキは有効に働くでしょう。
Dio110ライト 希望価格 税込227,800円

続いては原付二種随一のコスパを誇るディオ110の新基準原付版です。
スマートキーの無いディオ110ベーシックをベースモデルとしてコストダウン。基本的な装備は据え置きながら車体価格税込み約23万円を達成!(してほしい)
車重96kgという軽量スリムな車体に14インチのホイールを装備しており乗り心地や取り回しは良好。
スペック表には現れませんが、空冷エンジンながら静粛性が非常に高いのもポイント。早朝・深夜の移動でもご近所さんに気兼ねなく運転できます。お手軽&快適なホンダの新基準原付のスタンダードモデルとして人気を博します(僕の脳内で)。
リード125ライト 希望価格 税込310,000円

ギリギリプレミアムスクーターに分類されそうな価格帯ですが、ラインナップ拡充のためにリード125がリスト入りしました。
ベース車のリード125はPCXと共通のeSPエンジンを搭載しており、低燃費・低騒音・低振動ながら高出力という謎の出来過ぎマシンです。フラットフロアと12&10インチタイヤで乗降性抜群。加えて容量37Lという巨大なラゲッジスペースとフロントインナーボックス(内部にUSB-C充電端子有り)と豊富な収納を持ちます。街乗り買い物マシンとして優秀な一台です。
新基準原付化に際してスマートキーをオミットしコストダウン。ディオ110との絶妙な価格差でユーザーを悩ませまるのは原付二種版と同様です。
【空想】ヤマハはコンパクトな車体で勝負
- ジョグ125ライト
- アクシスZライト
ヤマハからは2車種のエントリー。どちらも前後10インチタイヤを採用しています。軽量な車体で取り回しに優れるので、原付一種からの車種転換もそれほど違和感なくできそうに思います。
ちなみにこの上記2車種以外のヤマハ原付二種はプレミアムモデルとなり、なかなか高価です。そのプレミアムモデルの中で一番安価なシグナスグリファス辺りはプレミア感とスポーティなスタイリングのバランスが良く人気も出そうなのでギリありな気もしましたが……。あとはビジネススクーターのギアが生産終了になったのは痛手ですが、ホンダのBENLY:eがOEM供給されるようなのでそこは問題なさそうです。
当面はこの2台に頑張ってもらいましょう。
ジョグ125ライト 希望価格 税込246,300円

車重95kgという現行原付二種トップの軽量ボディに10インチタイヤを組み合わせた軽快スクーター。シート高も735mmとかなり低いので原付一種からの乗り換えは一番抵抗なく行えるのではないか、ということで採用しました。
とにかくシンプルなスクーターで、LEDライトやスマートキーといった便利装備は当然ありません。ブレーキも前後ドラムブレーキという簡素さ。「通勤と買い物だけならこれで十分だよ」というミニマリスト・シンプリスト的思考の方にもオススメです。
アクシスZライト 希望価格 税込260,800円

車重100kg&前後10インチタイヤのコンパクトな車体に反して、37.5Lの大容量ラゲッジスペースを備えています。ステップボード前端の傾斜部分に足を置けるので、フロアに大きなカバン等の荷物も載せやすく積載能力は超優秀。ジョグ125と同様癖のないベーシックなスタイルのスクーターで、街乗り買い物マシンとしてリード125ライトに対抗できる貴重な車種です。
【空想】スズキはコスパと個性的スタイルで挑む
- アドレス125ライト
- アヴェニス125ライト
- バーグマンストリート125EXライト
現在スズキがラインナップする原付二種スクーターは全てフレームとエンジンを共有しており、低コストで多様なバリエーションを生み出しています。全車フラットフロアに12&10インチタイヤを採用し取り回しも抜群です。シート高は高めですが、カットフロアボードにより足つき向上の工夫がされているところに気配りを感じます。他社バイクでは珍しいキックスターターやUSB充電端子を標準装備してるのは嬉しいポイント。コスパを重視する方はスズキ車に乗りましょう。
アドレス125ライト 希望価格 税込250,900円

クラシカルなスタイルを持つスクーター。丸みを帯びた個性的なデザインが目を引きます。4種類の豊富なカラーバリエーションで好みの一台を選べます。スタイル重視の方はこちらがオススメ。
アヴェニス125ライト 希望価格 税込261,900円

こちらはエッジの効いたスタイリッシュなデザインのスクーター。シート下ラゲッジスペースの他にフロントインナーボックス&インナーラック、荷掛けフックを2つ装備しており優秀な積載性を備えます。
スズキ3車種中唯一リアブレーキロックレバーを備えているので、坂道での駐停車でも安心です。
バーグマンストリート125EXライト 希望価格 税込307,900円

のびやかなスタイリングのバーグマンストリート125EXライト(長い名前だ)は、短いながらも独立したスクリーンを装備しています。ステップボード前端が傾斜しているのでゆったりとしたポジションをとれるのでツーリングなどの長距離ライドも快適です。3車種の中で唯一アイドリングストップ機能を備えており燃費性能も優秀。アヴェニスと同等の積載装備の他に標準でリアキャリアを装備するので、買い物バイクとしても活躍できるポテンシャルがあります。
まとめ: 用途に合わせて検討しよう。じっくり考えて柔軟な選択を
現在、通勤や買い物のための移動手段を検討すると、電動キックボードをはじめとした特定小型原動機付自転車や電動バイク、電動アシスト自転車といった多くの選択肢があります。しかし純粋な走行性能の他に航続距離や車体価格の問題もあり、ある程度長距離の移動には、まだまだガソリンエンジンを搭載する50ccスクーターのメリットが大きいです。
もちろんごく短距離の移動しかしない方だったりバイク用駐輪場が利用できない立地環境の方は自転車を利用するほうがいいでしょう。
新基準原付はメーカーが残してくれた貴重な選択肢です。ひとつの選択にこだわらず、柔軟な思考で自身にマッチした移動手段を選択しましょう。

原付免許で乗れるコミューターを販売し続けてくれるメーカーには感謝だね。
利用者もルールをしっかり理解して正しい選択をしよう!




コメント